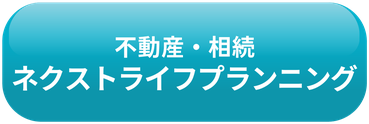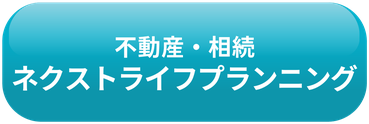相続の基本を知ろう(1)… 遺産分割
■遺言書は、相続対策の基本になる
実家の相続を理解するには、
相続に関する基本的な知識を押さえておくことは必須要素です。
誰が(法定)相続人になるのか、
それぞれの相続割合はどのくらいになるのかは、
以前のコラムでもお話ししてきました。
今回は、相続人は誰なのか特定したうえで、
少し深掘りした話をします。
まず、遺産分割で大切なことは、「遺言書があるか・ないか」です。
遺言書がある場合には、基本的に遺言に沿った遺産分割を行います。
遺言書がない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行い、
遺産分割協議書を作成する流れになります。
もし、被相続人の希望通り財産を分けたいのであれば、
遺言書を残しておくのが得策です。
遺言にはいくつかの形式がありますが、
「公正証書遺言」をおすすめします。
ほかには、「自筆証書遺言」という形式も選択肢のひとつですが、
これは書き方を誤ると無効になってしまう可能性があるものです。
相続が発生したあとで「検認」という手続きがあって、
手続きに入る前にかなりの時間をロスしてしまう、
といったデメリットがあることを覚えておいてください。
■遺言書には限界がある
遺言書には重要な役割がありますが、
限界があることをご存じでしょうか。
たとえば、誰かひとりにすべての財産を渡そうとすれば、
「遺留分」という相続人が持つ最低限の権利を
侵害してしまう恐れがあることです。
配偶者や子どもには本来の相続分の2分の1、
親御さんには3分の1の遺留分が発生します。
(兄弟姉妹には、遺留分はありません)
遺言書で財産を分ける際には、
遺留分を考慮することを忘れないようにしましょう。
また、遺言書を書く本人以外の相続について触れても、
有効性はありません。
たとえば夫が、
「将来妻が亡くなったら、財産は〜に渡す」
といった内容は、無効となります。
なお、
「(法定相続人ではない)孫に〜を渡す」
といった遺言は、もちろん有効です。
■遺産分割協議は、法定相続分にこだわらなくていい
遺言書が存在しない場合には、先ほどお伝えした通り、
相続人全員が遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成します。
この協議書は、銀行預金の引き出しや不動産の登記に必要です。
一般的に、「遺産の分割は法定相続分が基本」
と思っている人も多いのですが、
実際には法定相続分通りに分ける必要はありません。
極端なたとえですが、
相続人全員が合意すれば、
ひとりにすべての財産を渡すこともできます。
法定相続分は、たとえば相続税を計算するときや、
相続人の間で財産分けの折り合いがつかず、
裁判所が強制的に財産分けをするときに使う割合です。
遺産分割協議によって、
相続人以外にも渡すことはできますが、
ここは注意が求められます。
相続人以外の人が遺産分割協議に参加し、
相続人の全員が同意をして相続財産を受け取ったとしても、
税務上は相続人から財産の贈与を受けたものとみなされるのです。
ですから、財産を受け取った人には、
相続税よりも負担の大きい贈与税がかかります。
ここでお伝えしたいのは、
「法定相続分は権利だ」
と思っている人も多いのですが、
決してそうではありません。
基本的には相続人が全員合意すれば、
自由に分けることができるのです。
「決まりきった方法でしかできない」
という「受け身」の考え方にとらわれがちですが、
実際にはもっと主体的にできる余地があることを覚えておいてください。
■遺言書は、相続人以外にも財産を残しやすいメリットもある
相続人以外に財産を渡す場合もあるでしょう。
そのときには、遺言書が有効です。
遺言書に記載されていれば「遺贈」として扱われ、
贈与税ではなく相続税の対象となります。
「相続税」がかからない場合、
財産の分け方によっては遺言書の内容が重要になることがあります。
遺贈の場合は「相続税の2割加算」が適用され、
税額が変わってくるため、注意が必要です。
次回、相続税について詳しくお伝えしたいと思います。